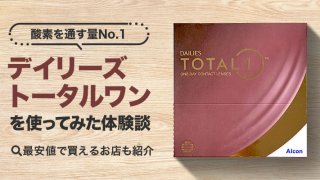コンタクトレンズをネットで購入する際に、さまざまな耳慣れない数値を聞かれたりします。店舗で購入する際には眼科でもらった処方箋をそのまま渡すだけですが、いざネットではじめて購入する際にはかなり迷いますし、不安が付きまといます。現在ネットで購入する方が増えているので、知っておくべきコンタクトレンズの数値の意味を解説します。
レンズ購入前にこれだけは絶対知っておこう!
コンタクトレンズを買う前に眼科で診察してもらうと、自分に適したコンタクトレンズのサイズや度数を調べてもらえます。量販店などのお店やネット通販で買う際にはこの眼科で調べてもらった数値を伝えて購入することになります。その中で絶対に必要で知っておかなければならない項目は以下の3点です。
その1:自分の症状(近視・遠視・乱視・老眼)のどれか?
目が悪くなったときに気にすべきは、
で症状が異なり、適したレンズの種類が異なります。
これはそれぞれ、近視・遠視・乱視・老眼で原因が違うため、その症状に適したコンタクトレンズ選びをする必要があります。
その2:度数(パワー、POWER、略:PWR)
ネットで購入する際に必ず聞かれるのがこの度数です。度数はPowerやPWRと表記されている場合があり、一応単位があってD:ジオプトリー(diopters)というのがあります。処方箋には-3.5とか+3.5などの表記がされ、ネット購入時には+10.0~-10.0までを自分で選択して購入することになります。それぞれの意味は以下になります。
度数の違い
近視・遠視の場合
近視・遠視で+とーが違いますので、注意して購入してください。近視は凹レンズなのでマイナス、遠視は凸レンズなのでプラスと覚えましょう。
私は小4のときに視力が0.3と診断されてメガネをかけ、延べ30年以上近視で目が悪いです。なのでコンタクトレンズの度数もかなり進んでいて現在両目で「-8.5」です。ただ視力低下は常に進行するわけではなく、ここ最近の10年くらいは「-8.5」から変わっていません。コンタクトレンズはー20くらいまであるそうですが、ネット上で販売されているものはそこまでのものはなく、だいたい-10前後までみたいです。なのでこれ以上悪くなるのは勘弁してほしいですね・・・。
遠近両用(老眼)の場合
遠近両用コンタクトレンズで知っておかなければならないのがこの「加入度数」です。加入度数は近くを見るための度数と遠くを見るための度数の差分です。自分に適した加入度数は眼科で測ってくれますので、40代以降で老眼に悩んでいる方は眼科に相談し、自分に適したレンズを処方してもらいましょう。加入度数が高いものから遠近両用コンタクトレンズを使用すると、慣れるまで時間がかかるため、数値の少ないものから試していきましょう。
その3:ベースカーブ(BASE CURVE略:BC)
ベースカーブとは、コンタクトレンズの円弧の曲がり具合です。数値の表記例としては「8.4」や「9.0」などです。値が大きいほどカーブが緩やかなので眼球が大きい方は、値も大きくなります。眼球の大きさは人それぞれなのでこれもしっかり選びたいところです。しかしながらほとんどのネット通販では、あまり在庫を抱えたくないせいか、1種類しか選べないケースがあったり、メーカーもカーブによって選べる度数に制限があったりするようです。大体の人が同じサイズだから大丈夫とも思いますが、「私は人より目のサイズが違うかも」という方は、必ず眼科でサイズを測ってもらいましょう。レンズのカーブが違うと当然違和感やレンズが瞳から浮いて外れやすくなったりするので注意しましょう!ちなみに私は「9.0」です。眼球が大きめということなんでしょうね。
形状に関する数値
直径(略:DIR)
コンタクトレンズの直径(円の大きさ)を指す数値で、よく「DIR」と略されていることがあります。これはほとんどの使い捨てコンタクトレンズでは商品ごとに選べることは少なく、その商品で固定になっています。ソフトコンタクトレンズは大体14mm以上で、ハードコンタクトレンズは大体8mm以上からあるようです。直径がおおきくなると、瞳を覆う面積が増えるので、目に届く酸素の量が減ります。カラーコンタクトレンズは瞳を覆う必要があるのでソフトレンズタイプしかないのは、このためですね。
中心厚(略:CT)
コンタクトレンズの中心の厚さを「中心厚」と呼びます。各製品ではこの中心厚をmmで示した数値が記載されており、度数により異なりますが、多くのメーカーが「度数-3.00の場合」を例に製品情報に記載しています。厚みがあればあるほど酸素透過性が弱まったり、瞬き時に引っかかりコンタクトレンズがズレたり外れたりする原因になります。より薄い製品を探してみるとよいですね。ちなみに私の「ワンデー アキュビュー トゥルーアイ」は度数が-8.5で中心厚が0.086mmです。
エッジ厚
コンタクトレンズの周りの厚さをエッジ厚と呼びます。これも薄い方が装用感が滑らかになります。
マーク
ソフトコンタクトレンズで仕様欄にマークありなしがある場合があります。これはレンズ表裏の見分けがつきやすくするために、文字が印字されているかどうかです。「1day」とか「123」と記載されています。従来の表裏を見分ける方法としては、指の先にレンズをおいてカーブが丸まっているか反り返っているかを見分ける必要がありましたが、これがかなり微妙な見分け方でした。表裏を間違えてつけてしまうと違和感が出てしまうので、このマークありなしは利便性の面で重視してもよいでしょう。ちなみに私は慣れているのでマークなしのものを使っています(笑)
カラー
仕様欄に書かれているカラーは、コンタクトレンズに施された薄い着色のことです。レンズに薄い着色を施すことで、洗面所や床に落ちても探しやすくするため用いられています。「レンズ着色」や「レンズカラー」などと記載されていることもあります。カラーコンタクトの色と混同しがちなので注意が必要です。私は薄い水色なので洗面所に落ちてもすぐ見分けがつきます。昔は透明で探すのに苦労しました。。。
性能に関する数値
酸素透過係数(略:Dk値)
これは簡単に言いますとレンズが酸素を目に届ける量を示す値です。Dk値と略されていることがおおいです。
コンタクトレンズの装用感を左右するといってもいいのが酸素透過量です。なぜ目に酸素が必要かというと、簡単に言えば目は口と同じように酸素で呼吸していて健康を保とうとします。その呼吸が出来なることで不健康になり、細菌感染や血管の眼病を引き起こします。
私の母親はこれで血管が角膜内に入り込み手術していました。(※母親も1980時代からのコンタクトレンズユーザです。)
酸素透過率(Dk/t値またはDk/L値)
前述の酸素透過係数をレンズの厚みで割った値が酸素透過率です。酸素透過係数Dk値÷レンズの厚みt値(またはL値)で出た値ですが、この辺になると専門領域の知識が多くなり、説明がややこしくなるので、結論を言うと「酸素透過率が高いほうが酸素を通しやすいよいレンズ」と覚えましょう。以下にメジャーな製品のそれぞれの値をご紹介します。
1Dayソフトコンタクトレンズの各メーカー製品酸素透過率比較
| メーカー | 製品名 | Dk値 | Dk/L値 |
| ボシュロム | アクアロックスワンデー | 114 | 163 |
| アルコン | デイリーズ トータル ワン | 140 | 156 |
| J&J | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | 100 | 118 |
| メニコン | 1DAYメニコン プレミオ | 64 | 91 |
| SEED | 1dayPureうるおいプラス | 30 | 42.9 |
| Sincere | エルコンワンデー55 | 20.3 | 25.4 |
| CREO | クレオワンデーUVモイスト | 20 | 25 |
調べた結果、酸素透過率が高い製品としてボシュロム社の「アクアロックスワンデー」が1位になりました。
Dk値ではアルコン社の「トータル1」が1位でした。そういえばCMで「生感覚・・・」とかのキャッチコピーでやってましたね笑。眼病予防などを気にされる方は酸素透過率の高いレンズを選びましょう!
含水率
コンタクトレンズが水分を吸収する値です。含水率は「がんすいりつ」と読みます。「ふくすいりつ」ではありません。(※私は間違えていました笑。)この含水率は高ければよいというわけではなく、多い少ないでそれぞれメリットとデメリットがあります。
| 含水率 | メリット | デメリット |
| 高い |
|
|
| 低い |
|
|
・・・でどっちがよいかというと、どっちも特性があるのでこれがよいというものはなく、使い方やこだわりによって選ぶ必要があります。
たとえば付け心地がよく目にも優しいのであれば含水率が高いもので、目薬や涙で常に潤った状態を保てば総合的によいのではないでしょうか?
目が乾きやすく、目薬が面倒な方は、含水率が低めの製品の方がよいでしょう。
上記で調べた各製品の含水率の数値は以下になります。【注】メーカーからは含水率が高い製品と低い製品をそれぞれ分けて出しているところがありますのであくまで個々の製品の値です。
| メーカー | 製品名 | 含水率 |
| CREO | クレオワンデーUVモイスト | 58% |
| メニコン | 1DAYメニコン プレミオ | 56% |
| Sincere | エルコンワンデー55 | 55% |
| J&J | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | 46% |
| ボシュロム | アクアロックスワンデー | 46% |
| SEED | 1dayPureうるおいプラス | 38% |
| アルコン | デイリーズ トータル ワン | 33% |
上記でアルコン社の「デイリーズトータル1」は内部の含水率は33%と記載されていますが、表面の含水率が100%なんだそうです。たしかにまるで「生感覚」ですね!笑
視感透過率
レンズが光を通す比率を「視感透過率」といいます。視感透過率=0%はまったく光を通さない状態です。たとえばメニコン社の「Magic」という製品は視感透過率が94%とあります。同じくメニコン社の「メニコン1DAY」は視感透過率が97%だそうです。参考に眼鏡の保護レンズなどでは視感透過率が85%くらいで、サングラスはそれよりも低い値になります。
紫外線吸収率
紫外線つまり「UV」を吸収する率です。UVカットを謳っているコンタクトレンズではこの「紫外線吸収率」「UVカット」がxx%と記載があります。数値が高いほど紫外線をカットします。そもそも目が紫外線を長時間浴びるとどんな影響があるかというと、結膜炎や白内障の原因になったり、日焼けで肌を黒くするメラニンの分泌を促進してしまいます。天気のいい日に長時間、外で仕事をしたり、遊んだりする場合は、紫外線吸収率が高いコンタクトレンズか、もしくは紫外線吸収率の高いサングラスを併用したほうがよいでしょう。コンタクトレンズもサングラスも選ぶときには紫外線吸収率が高いものにこだわりたいですね。
種別に関する記載
コンタクトレンズ分類
よく製品情報に「コンタクトレンズ分類」または「FDAグループ」と書かれている場合があります。これは以下のそれぞれを分類して記載しています。
- グループⅠ:非イオン性・低含水
- グループⅡ:非イオン性・高含水
- グループⅢ:イオン性・低含水
- グループⅣ:イオン性・高含水
それぞれのメリット・デメリットは以下になります。
| メリット | デメリット | |
| 非イオン性 | レンズが汚れにくい | レンズが硬め |
| イオン性 | レンズが柔らかめ | レンズが汚れやすい |
| 低含水 | 目が乾きにくい | 装用缶が悪い |
| 高含水 | 装用缶がよい | 目が乾きやすい |
それぞれの短所と長所を見極めて購入すれば、自分のこだわりに合っているレンズ選びができるようになります。ちなみに私は「ワンデー アキュビュー トゥルーアイ」を使用しおり、分類は「グループⅠ」になります。非イオン性で低含水なので、上記を参考に言い換えると、「レンズが汚れにくく、目が乾きにくいので長時間の装用におススメだが、レンズが柔らかくないので装用感が比較的に悪いですよ」という商品を選んでいることになります。上記を参考に自分が使っているレンズが適しているかどうか皆さんも調べてみてください。
その他記載
構成モノマー
コンタクトレンズの箱の中にある添付文書内に「構成モノマー」なる記載があります。これはカンタンに言うとコンタクトレンズで使用している素材になります。素材によって酸素透過性や含水率の性能がことなります。
使用期間
そのコンタクトレンズを使用してよい期限です。大体の場合、コンタクトレンズの箱に記載があります。箱から取り出して保管していると、期限がわからなくなるため、不用意に箱から取り出さないようにしましょう。私の場合はかばんの中に保険として2,3使い捨てレンズを入れっぱなしなので、いつまでの期限かわからなくなっています。持ち歩き用のコンタクトレンズもこまめに取り替えたいですね。
医療機器承認番号
コンタクトレンズは高度管理医療機器という分類で、その製品の認証(審査)を通過したことを証明する番号が「医療機器承認番号」です。審査の主管は厚生労働省医薬・生活衛生局になります。日本で販売されている製品はカラーコンタクトも含め、この安全審査を通過していますが、海外で販売されているコンタクトレンズはこういった審査基準が国ごとに異なるため注意が必要です。
まとめ
コンタクトレンズの数値には、度数以外にもいろんな意味があります。その製品が持つ特性と、自分が欲している性能が本当にマッチしているか?を調べてみると、眼科で勧められたレンズもよい製品にめぐり合うかもしれません。
すべての人に万能なレンズはなく、装用時間・使用頻度・スポーツの激しさなどで自分のライフスタイルごとに利便性が高い製品を選べるようになりたいですね。